PFI事業と病院 栗原 嘉一郎
はじめに
PFIについて、筆者はこれまでに若干の見解を述べてきた(文1・文2)。ここでは進行中の病院事例について触れながら、より具体的に論を進めたいが、多少の重複を避け得ない点はご容赦頂きたい。またPFIが提起している問題の多元性から見て、その評価は立場によって異なるものと思われるが、1建築人として極力公共建築の持つべき本質的な次元に立って考えを述べてみたい。
文1:「PFI事業を魅力あるものにするために」栗原嘉一郎、建築雑誌2006年2月号
文2:「PFIと病院建築」栗原嘉一郎、INFORMATION FROM JIHA、2003.6.1
PFIのあらまし
官から民へという大きな流れの中で誕生したPFI(Private Finance Initiative)は、1999年7月に基本法、翌年3月に同基本方針が公布されて以来徐々に浸透しつつある。PFIは端的に言えば、国や地方自治体が必要と考える公共施設の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力および技術的能力を導入し、国や地方自治体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスの提供を図るという事業方式である。
事業のプロセスは行政が必要と考える特定の事業を選び、それをPFI方式で行う場合の財政削減効果VFM(Value for Money)について検証し、その有効性を確かめた上で実施計画を策定・公表し、事業者を公募する。参加を希望する事業者は、当該事業を行うのに必要な関連企業を傘下に集めた特別な会社SPC(Special Purpose Company)を設立し、行政から示される課題について回答としての提案書を提出する。資格要件ならびに提案書の審査を経て選定された事業者は、行政との間で細目にわたる協定を締結した上で事業を実施する、という手順を踏む。
この方式は国や地方自治体にとって、従来自らが行ってきた社会資本の充実や公共サービスを、自身が行うより安くかつ高い質で提供できる方式として関心を集め、これまでに実施方針が策定・公表された事業数は平成18年11月10日現在で国33、地方公共団体189、その他の公共法人29、計251件に達している。一方SPCを立ち上げるのは商社・金融業・ゼネコン・不動産業等だが、中でも大手ゼネコンは事業の領域が大きく広がるメリットを生かすべく、積極的に体勢を整えている。
病院事例
上記のうち病院の事例は9件だが、このうち既に供用開始しているのが近江八幡市立総合医療センター(2006年10月開院)・高知医療センター(2005年3月開院)・八尾市立病院(2004年4月開院)の3例、工事中のものが島根県立こころの医療センター、事業契約まで終えたものが多摩広域基幹病院+小児総合医療センター、選定中のものが都立がん・感染症センター、公募中のものが愛媛県立中央病院・神戸市立中央市民病院・大阪府立中宮精神病院となっている。このほか準備が進んでいるものが3例ほどある。
ここでは既に供用を開始している3例に多摩広域基幹病院+小児総合医療センターを加えた4例(以下、<近江八幡>・<高知>・<八尾>・<多摩>という)の状況にも触れながら、病院PFIを中心に筆者としての所見等を述べてみたい。因みに4例の病床規模はそれぞれ407床、648床、308床、1350床(750床+600床)である。
PFIの事業範囲と病院
これまでにわが国で実施されたPFI事業は、事実上建設費の割賦払いを主目的とした施設建設とその維持管理業務にとどまるものが多かった。これでは、公共サービスへの民間活力の導入によってより質の高いサービスをより低廉なライフサイクル・コストで提供しようというPFIの狙いに照らして好ましくないとの声が上がり、改正PFI法(2005年8月施行)ではその目的に「国民への低廉かつ良好なサービスの提供を確保する」ことが追記され、ソフト分野への事業範囲の拡大を誘っている。
この点から見ると、病院は専門性の高い医療関連サービスを幅広く抱えており、SPCに委託しうる事業範囲が極めて大きい事業といえる(表)。
前記事例について言えば、<八尾>は、運営のみのPFIだが、期間15年の事業として成立している。また<近江八幡>・<多摩>は事業範囲として施設整備(設計・施工)から運営までを含む、いわばフルセットのPFIであり、<高知>は上記から設計業務を除く範囲を事業範囲とするPFIだが(期間はそれぞれ30年、15年、30年)、総事業費のなかで施設整備費の占める割合はどれも20~30%程度にとどまっている。運営の占める比率が70~80%に達するということだ。24時間稼動という特性も手伝っての病院ならではのソフトの厚みを示すものである。
この点から見て病院PFIへの期待は高いようであり、参加事例は増えていくものと思われる。
表:病院の運営に関わる民間業者の 事業範囲モデル(文3より作成)
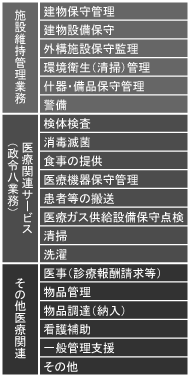
PFIの成果の一端
PFIの最大の眼目である国・地方自治体にもたらす財政上の効果についてはその仕組みから言って間違いなく、実例では当初の想定を上回るVFMを挙げている場合も多いようだ。病院事例でも、<近江八幡>では当初想定値の5~8%を大幅に上回る14.4%もの効果が約束される結果となっている。この中には長期にわたるメンテナンス費用の合理化を追及した結果として得られた建設費の縮減が含まれていることはいうまでもない。
より高いサービスが実際に提供できているかどうかの検証は先行例といえども未だ時を経ていない現在では今後に待つほかないが、<高知>の場合、開院1年後の2006年3月時点において平均在院日数は当初想定した18日を越えて13日前後となっているほか、患者本位の医療を目標に明示し、その一環として患者の苦情や意見の積極的な吸収を図った結果、患者の満足度が目に見えて向上したことなど、プロセスを重視したSPCとの協働の成果が既に表れている(文4)という。
また開院2年余を経た<八尾>では、市職員の人員削減が達成されている上、給食における選択式メニューの実現、柔軟な人員配置による夕刻以降の患者や医師等の利便性の向上、SPCの一括管理による隙間業務の解消等、運営面の質的向上が実現し、患者の評判も良好という。
総括的な言い方をするなら、施設の維持管理はもとより、多種にわたる医療支援業務ならびに対患者サービスを、経営的な観点をも含めてSPCが予め約束した高い水準に保ってくれるとすれば、医師・看護師は文字通り診療・看護に専念できるし患者満足度も高くなる筈で、受益者側からのメリットは基本的に大きいものになるに違いない。
文4:「PFI事業の導入と事業評価」瀬戸山元一、「病院設備」272号、日本医療福祉設備協会
若干の問題点
1)過大な応募者負担と限られる参加企業
PFI事業に参加するには、代表企業となるSPCのもとに関連企業がコンソーシアムを形成し、行政から示される広範かつ膨大な要求課題に対して提案書等を作成して応募することになるが、手弁当で行われるこの作業量が半端でない。何しろ行政から渡される各種資料のボリュームは病院事例4例について言えば要求水準書を含めてざっとA4で1000~2000頁に達しており、応募者の提出する提案書も数百頁、<多摩>の場合では規模が大きいとはいえ何とおよそ3000頁にも達したと聞く。数グループが応募するとして、注がれるエネルギーや費用の総量は目も眩むばかりだ。これで選定されなければ勿論水の泡。精神的徒労感をも含めて投じられるエネルギーの損失は社会的に問題とすべき量に達している。
こうした過度の負担は結果としてPFI事業への応募意欲の減退を招き、応募数自体の減少が目立ってきたようだ。病院事例においても、島根県立こころの医療センターの場合、応募数は1社にとどまり、事実上無競争であった。
中でも建築設計業務がこの中に含まれる場合の設計事務所の負担は過酷というほかないように思われる。多岐にわたる運営業務の検討に当たっては、その下敷きとして全体的にも部分的にも常に建築平面が求められ、コストの縮減に向けてその間に絶えず調整が求められるからだ。大事務所でなければ耐えられないに違いない。
また、SPCが関連異業種を集めて応募のための膨大な作業を進めるという形態は、同種のプロジェクトが続けば自ずとメンバーの組合せが固定化する結果を生むであろうし、SPCからコンソーシアムの構成員として声がかかるのは一部有力企業に限られるであろうことを考えると、声のかからないであろう多くの中小企業が公共施設の建設や運営に関わる道が閉ざされる結果を生むであろう点が気にかかる。
2)要求水準の示し方について
PFI事業において行政が応募者に手渡す資料の中で実質的に最も重要なのが、求める施設ならびにそこで提供されるべきサービスの水準を記した要求水準書だが、これが何とも膨大で細かい。応募者に過大な負担を強いるもとである。
施設計画についていえば、ほとんど全所要室にわたる細かな機能要求、床面積、床・壁・天井の仕上げ、各室に備えるべき備品の数々、採光・通風・遮音吸音・日影等々に対する指示に至るまで何とも細かい。運営面の業務要求内容も同様、微に入り細に入り示されている。要求を細かく具体的に示せば示すほど応募者側の創意工夫の余地が狭まることは間違いなく、施設計画の面でいえばパズル解きに終始して伸びやかな提案は望めまい。
要求水準について、PFIの元祖である英国の担当官ブレーザー氏は「公が必要とするサービスを決める時に重要なことは目的を決めるのであって手段に立ち入ってはならない。それは民間のイノベーションに任せるべきだ」と語っている(文5)。内閣府自体、自らが定めている条例において「民間事業者の創意工夫が極力発揮されるよう、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すことを基本とし、建造物、建築物の具体的な仕様の特定については必要最小限にとどめること(抄)」としている。
長期にわたる運営を前提とした契約を特徴とするPFI事業に対し、要求水準書作成担当者が当面の要求や現時点で持ち合わせている価値観によって細部に至るまで縛りをかけてしまうのは、事業の主旨に反しているように思われてならない。
医療・福祉施設のほか教育・文化施設等、広く市民の利用に関わり、そのあり方に色々な可能性・発展性があるような施設の場合は、応募者に対する要求水準は、端的に 言えば、当該プロジェクトの持つ基本理念とそれに基づく本質的目標値にとどめるとともに、求める提案内容については必要とする項目の提示にとどめるくらいの方がよいはずだ。当初の導入可能性調査段階でVFMの検証を経た価格の中で、個々の項目が到達すべき具体的な水準や仕様は応募者が提示して競うべきものではなかろうか。
病院についていえば、そのありようは今激しく変わりつつある。在院期間の短縮が進みベッド数が減少する中にあって、医療は高機能病院と家庭医療の二極化に向かうとみられる。個々の自治体病院には、地域の実情とのからみの中で将来に向けての役割の明確化とその実体化へのプログラムづくりが問われている。そこにおいて例えば20年なり30年なりを事業期間とするPFI方式で施設整備等を行うとするなら、その間の地域動態予測をベースに病院が果たすべき役割や機能グレード、入院期間等診療上の目標値、関連サービスの質を示す指標等々を厳選して提示し、それを満たす方法とか施設の規模・構成などは、その間の展開過程をも含めて、一切事業者の提案に待つといったやりかたもあるように思う。問われるべきは現時点における詳細な要求への対応力というよりは、当該プロジェクトの長期にわたる機能・施設・運営の変化発展に対応すべきプログラムの構築とその裏づけではなかろうか。少なくとも、現時点での事細かな要求事項への対応を応募者に求め、将来の変化に対してはモニタリング条項で対応すればすむというようなレベルの話ではないと考える。
因みに要求条件が定形化しにくく、事業者の柔軟な創造力が求められるこの種のプロジェクトにおいては、事業者の選定方式として一般競争入札方式は馴染まないとされる。文3においても、病院PFI 事業における民間事業者の募集・選定は、プロポーザル方式が望ましいとしている。公募時に契約および価格の概要を提示した上で、提案を求める過程において発注者側との間で必要なコミュニケーションを図る必要があるからとしている。
なおこの点に関し、そもそもPFIとして実施するには適当ではない性格のプロジェクトとして、「大規模なものや要求条件の複雑なもの等、発注者と受注者がやりとりを交わしながら建物のありようを作り込んでいく必要のあるもの」・「要求条件のすべてを発注時点で確定できない事情のあるもの」ほか2点を挙げている論(文6)もあるが、この考えによるなら、病院をPFI事業に乗せるのはそもそも無理なのかもしれない。
文3:「病院PFI推進ガイドライン」2003、10、(社)日本医業経営コンサルタント協会
文5:「医療福祉PFI」森下正之他、日刊工業新聞社
文6:「PFIの課題と展望」野城智也、公共建築184号
応募提案に対する評価の問題
事業者の選定は、提出された提案書ならびに価格について審査委員会が行うが、多岐にわたる評価項目とそれぞれに与えられる配点は、発注者当局ならびにコンサルタントによって事実上予め決められている。当然のことながら結果は配点ならびに採点ルールによって大きく左右される。
<近江八幡>では提案内容に対する評価500点、価格に対する評価500点、計1000点で4社によって競われたが、提案内容についての積み上げ方式による採点のばらつき幅は満点に対して4%弱であったのに対して、価格に対する評価点のばらつき幅は採点ルールの違いによって24%となり、結果として価格差の方が大きく作用する中で提案内容・価格の両アイテムにおいてともに2位であった企業体が総合で1位となった。
<高知>ではまず提案内容に対する評価点として1000点を与えて4社から上位2社を選び、次いでその2社のうち価格の安い方を選ぶ、というルールで選定した結果、提案点では2位であった企業体が逆転1位となった。
<多摩>は性能評価点210点、価格点90点、計300点を満点とする配点によって3企業体によって競われたが、性能評価に対する採点ルールとして項目ごとに1位を100点、2位を50点、3位を零点とするというドラスティックな方法が採られたため提案内容の評価点のばらつきが極めて大きくなり、ここで1位を得た企業体が価格面では最も高かった(従って価格評価点は最下位)にもかかわらず総合点で1位となり選定された。
採点方式の標準化や統一を図る必要はまったくないと考えるが、PFI事業においては当初にVFMによる価格面の検証をすませているのだから、評価の段階では提案内容に対する配点を極力大きくすることが重要だと考える。
提案内容自体の中での配点ももとより重要である。建築設計を事業範囲に含む場合、それに対して与えられる配点は、応募作業の過程における比重の重さや、建築はそれが出来てしまえば簡単に変えることはできず長期にわたって使用・運営のありようを制約することになる点からみて、それに見合う十分なものでありたい。
建築設計業務とPFI
既に供用開始している<近江八幡>・<高知>・<八尾>において、それぞれの建築設計担当者はPFIをどのように受け止め評価しているのか、インタビューを試みた。
<近江八幡>は設計事務所とゼネコン設計部の共同作業で設計が進められたわけだが、応募時の労苦に加えて、選定されて以後の作業は、性能発注を仕様発注に翻訳して置き換える作業、運営関連業者からの要求の吸い上げ、病院各部門との数知れぬ打ち合わせ、施工担当現場所長との意志疎通等によって、応募時の図面とは内容においてほぼ入れ替わったほどの大きなものとなったという。にもかかわらず、それらを通して総合的なライフサイクル・コストの縮減という未経験の命題に関係者一同で取り組み、高い水準で成果を挙げた誇りと満足感に支えられて、この方式に対する評価はかなり高かった。尤も設計作業を含むこの方式の評価について、設計事務所とゼネコンとでは若干の温度差があり、設計事務所側には、アイディアを出しながらも結局はコストを握るゼネコンに従わざるを得ない結果になることへのある種の悲哀感も感じられた。このことは、SPCとしてのゼネコンの下で設計が行われる場合の基本的な問題点といえるかもしれない。
<高知>は実施設計終了後のPFIであるが、SPCから出された基本理念「患者中心の医療の実践」に沿う形でのVE提案についての検討作業、図面を下敷きにしての運営側・施工側による数々の運営シミュレーションならびにオペレートデザイン等を経た結果として極めて多くの設計変更を要したにもかかわらず、結果として当初の設計以上のものになったとの肯定的な総括であった。出発点に設計図が既にあるということが、コストの算出効率を含めて極めて有効に機能した点が高い評価につながっているのであった。ただし、その過程において数多く出された問題点についてSPC側の調整力が弱く、その分まで設計者の負担増になったとの声も聞かれた。
<八尾>は竣工以後の運営PFIだが、その事業範囲に入っている医療機器・家具・備品等の選定や配置、運営面についての設計時の想定との調整などについて、建築設計者とのコンタクトが一切絶たれた形で行われたため、設計意図との食い違いを生じている部分が散見される点、設計者からは不満の声が聞かれた。運営PFIの場合、SPCとしては完成建物が引き渡される立場になるとしても、竣工前のなるべく早い時期にSPCの選定がなされ、設計者とのコミュニケーションを図った上で極力ハードとの調和にも留意した運営を行うことが望まれよう。なお<八尾>については、施設の建設を含まないPFIであるために維持管理に費用の嵩む贅沢な設計になっている、とする他のPFI関係者による批判的な声も聞かれた。PFIに対する立場によって評価の分かれる点であろう。
建築の基本設計を独立させてはどうか
建築の基本構想を含む形で選定されている<近江八幡>はもとより、実施設計を終えた上での<高知>にしても、PFI事業の進行する中での医療スタッフならびに関連企業との協議を経て合意に至るまでの設計作業に要したマンパワーは極めて大きかったようで、結果的に二度手間三度手間になっているようにも見受けられた。これは応募者側だけの問題ではない。行政から示される水準書をみると、その作成に当たって建築系コンサルに想定設計を行わせている場合も多いことがわかる。これをも含めれば、設計作業に投じられているエネルギー量は更に大きくなる、というより非生産的な無駄が多くなっているように思われる。
事業に先立って、PFIを前提にした公募式プロポーザルなどを通して設計者を選び、医療スタッフとの基本的な協議を経た上で基本設計までは公共側で固める方が良いのではなかろうか。
更に言えば、これは単に手間の問題というだけではなく、建築の価値評価を経済論理が強く支配するPFI事業の中の1要素として埋没させるのではなく、建築自体が持つべき諸般の側面を含めた視点によって独立に案を選ぶ方がよいと思われることにもよる。税金で建てられる公共施設としてライフサイクル・コストは極めて大切な要素には違いないが、自治体には、民間の論理からは漏れてしまいがちな側面を支える使命も同時にある筈だ。税金を投じる建物だからこそ高い先見性に支えられた機能性や地域の歴史性を見据えての都市資産としてのデザイン性や文化性が求められるという側面だ。公共施設の設計のすべてを経済論理が強く支配するPFIシステムの中に絡めとってしまっては、そうした点に関わる建築の質の確保が怪しくなることが危惧される。
それでもなお建築設計構想を事業範囲に入れるのであれば、既に延べたように、施設計画についての要求水準を簡潔かつ柔軟なものとして建築設計者の持つ創造性を十二分に発揮させ、そこに多くの配点を与える方向の運用が望まれよう。
